「ヒーローとは、誰かに信じられること」。
その言葉を裏付けるように、『To Be Hero X』は“信頼”を力に変える物語として誕生した。だが、この世界観には数多くの“元ネタ”と“伏線”が隠されている。『To Be Hero』シリーズとの繋がり、中国アニメ文化の影響、そして監督リ・ハオリンの過去作から受け継がれた思想――。本稿では『To Be Hero X』の元ネタと制作背景を徹底的に掘り下げ、「なぜこの作品が生まれたのか」を紐解いていく。
- 『To Be Hero X』とは何か──リ・ハオリン監督が紡ぐ日中合作アニメの核心と“元ネタ”を読み解くための前提
- リ・ハオリン監督の思想を辿る──『To Be Hero X』の元ネタに息づく“信頼”と“記憶”の物語設計
- 『To Be Hero X』の元ネタ①──“信じられることで力を得る”という設定に隠された現代社会と神話の構造
- 『To Be Hero X』の元ネタ②──『Link Click』から継承された“時間”と“他者”のテーマが織りなす精神的連鎖
- 『To Be Hero X』の元ネタ③──3Dから2Dへの転換が示す、アニメ表現と“信頼の原点”への回帰
- 日中合作が生んだ新たな“元ネタ”──『To Be Hero X』が切り拓く国境を越えるアニメ表現の未来
- 『To Be Hero X』の元ネタを超えて──リ・ハオリン監督が描いた“信じる力”が導く次なる物語の行方
- まとめ──『To Be Hero X』が描いた“信頼”という名の未来
- FAQ(よくある質問)
- 参考・引用情報
『To Be Hero X』とは何か──リ・ハオリン監督が紡ぐ日中合作アニメの核心と“元ネタ”を読み解くための前提
2025年春に放送が始まった『To Be Hero X』。その第一印象は、派手なアクションとスタイリッシュな映像が際立つ“ヒーローアニメ”だ。しかし本質はもっと深い。リ・ハオリン監督がこれまでのシリーズを経て到達したのは、「信頼」そのものをエネルギーに変える世界観だった。
本章では、『To Be Hero X』の概要とシリーズ全体の流れを整理しながら、作品の“元ネタ”としての思想構造を読み解く。単なる続編ではなく、現代社会を映す鏡として生まれた理由を探っていこう。
シリーズ三部作で見えてくる“信頼”の進化
『To Be Hero X』は、リ・ハオリン監督が10年にわたって描いてきたシリーズの集大成だ。
- 2016年『To Be Hero』──崩壊した家族の中で「父の信頼」を取り戻す物語。
- 2018年『To Be Heroine』──少女が「他者を信じる」勇気を描いたスピンオフ。
- 2025年『To Be Hero X』──「社会がヒーローを信じる」ことが力となる新時代。
この3作を通して監督が探り続けたのは、「誰が、誰を、どのように信じるか」という構造だ。つまり“信頼の変遷”こそがシリーズの元ネタであり、その結実が『To Be Hero X』なのである。
ヒーローが“信じられる存在”として立つ世界
『To Be Hero X』の舞台では、人々が抱く信頼がそのままヒーローの力の源になる。信頼を失えば能力が消え、誰からも信じられなければ存在すら曖昧になる。これは単なる能力バトルではなく、「信頼が可視化された社会」の寓話である。
この設定の背後にあるのは、リ・ハオリン監督の社会観だ。SNSのフォロワー数や“いいね”の数で価値が測られる現代。監督はそこに潜む「信頼の危うさ」を物語化した。
“日中合作”というもう一つの元ネタ
『To Be Hero X』は中国のbilibili、日本のAniplexが共同製作する国際プロジェクトでもある。この協働体制そのものが“信頼”を象徴している。文化も言語も異なる国同士が、ひとつの物語を信じて紡いでいく──この制作背景もまた、本作の隠れた“元ネタ”のひとつなのだ。
参照:
公式サイト(tbhx.net) /
Wikipedia – To Be Hero X
リ・ハオリン監督の思想を辿る──『To Be Hero X』の元ネタに息づく“信頼”と“記憶”の物語設計
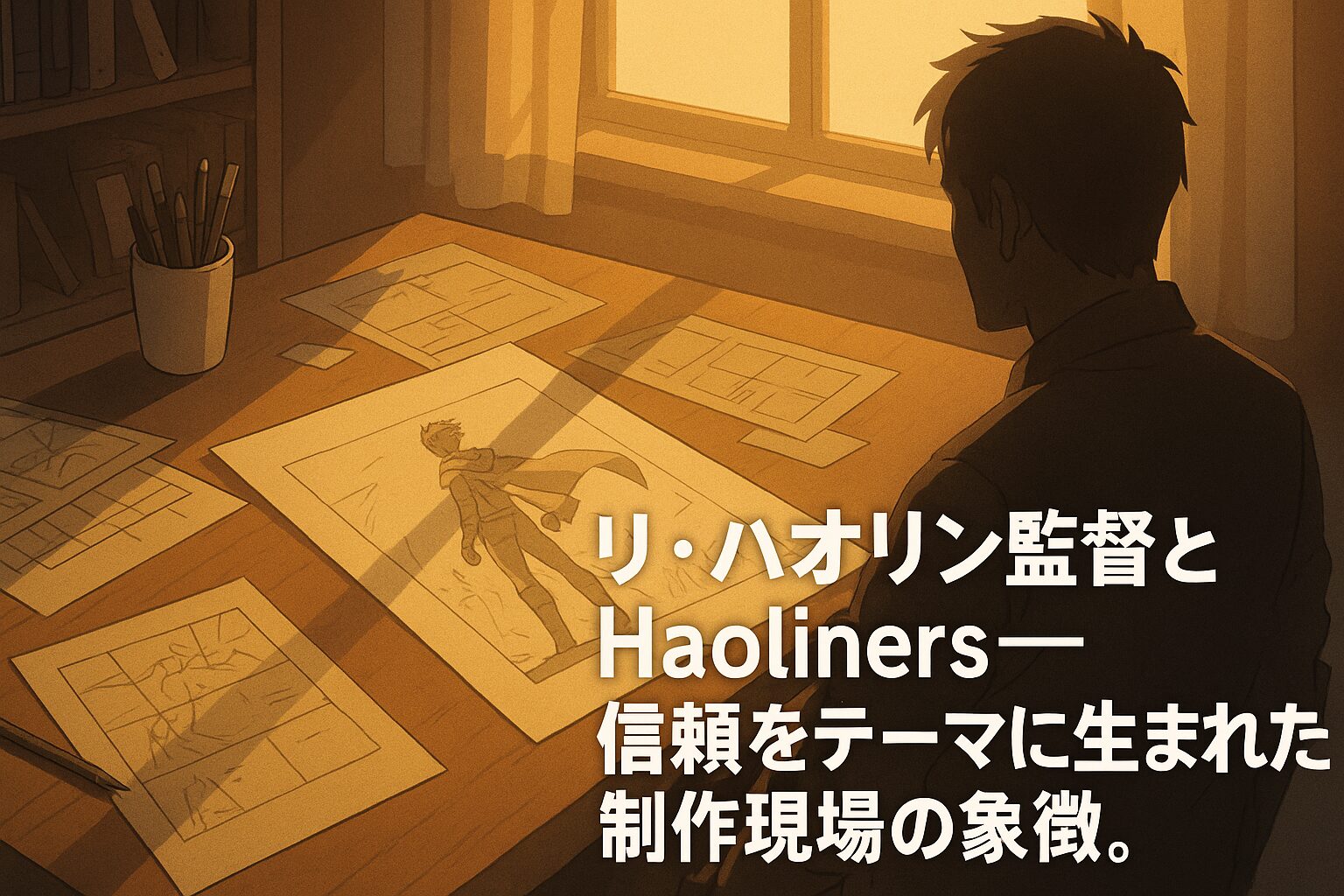
『To Be Hero X』を真に理解するには、監督リ・ハオリン(李豪凌)の思想に踏み込む必要がある。彼が生み出すアニメには必ず「時間」「他者」「信頼」という三つの軸が存在する。どの作品も、過去と現在、人と人の心を“見えない糸”で結び直す試みなのだ。
この章では、リ・ハオリン監督の創作哲学と、『To Be Hero X』の元ネタとして流れる“信頼と記憶”の関係を掘り下げていく。
Haolinersという制作集団──「信じ合うこと」から始まったスタジオ
リ・ハオリンは、中国・上海を拠点とするスタジオ「Haoliners Animation League」の創設者であり代表。もともとは日本アニメ文化に深く影響を受けながら、「東アジアの感情を共有するアニメ」を志して設立された。
彼の制作理念は明確だ。アニメとは、国境を越えて“感情を共有する装置”であること。だからこそ『To Be Hero X』は、単なるヒーロー物語ではなく、「信頼そのものを描くための共同実験」として企画されたのだ。
『Link Click』との思想的な連続性
リ・ハオリンのもう一つの代表作『Link Click』(2021)は、“他人の時間に入り、過去を修正する”という設定で世界的に評価を得た。『To Be Hero X』ではそのテーマが“信頼の時間”へと進化している。
『Link Click』が「過去を改変して救う」物語だったとすれば、『To Be Hero X』は「信頼を継続して守る」物語だ。つまり彼の中で「時間」と「信頼」は同義であり、どちらも人をつなぐ見えない記憶の回路として描かれている。
「信じることは最も難しい力」──監督自身の哲学
リ・ハオリンはインタビューの中で、こう語っている。
「この世界では、信じることこそが一番難しい力なんです。」
この言葉こそ、『To Be Hero X』の元ネタの根幹にある思想だ。
“信頼”とは、強さではなく脆さの象徴。人は互いに信じることでしか生きられない──そんな現代的な真理が、この監督の語るヒーロー像を形づくっている。
“信頼”が時間を越える――リ・ハオリン作品の核心
彼の作品では、信頼は常に「時間を超える力」として描かれる。
過去に信じたものが現在の自分を形づくり、現在の行為が未来の誰かに信頼として届く。
この構造は、まさに『To Be Hero X』における“力の発現”そのものである。
リ・ハオリンにとってのアニメは、映像ではなく信頼の記録。
『To Be Hero X』は、視聴者にその信頼を託すための物語装置なのだ。
『To Be Hero X』の元ネタ①──“信じられることで力を得る”という設定に隠された現代社会と神話の構造
『To Be Hero X』の物語を最も象徴する要素は、「人々の信頼がヒーローの力になる」という設定だ。
この一文だけを抜き取っても、そこに現代社会と神話の両方が交錯する壮大なテーマが潜んでいる。
本章では、この構造がどのように誕生したのか──つまり『To Be Hero X』の最も核心的な“元ネタ”を掘り下げていく。

信頼が力に変わる世界観──“信仰”を現代に置き換える試み
ヒーローが信じられるほどに強くなり、信頼を失えば力を失う。
この構図は、一見すると斬新に見えるが、実は古代神話にも通じる古いモチーフだ。
たとえばギリシャ神話では、神々は信仰を糧に力を得る存在として描かれる。
人々の祈りが途絶えた神は力を失い、やがて忘れ去られていく。
『To Be Hero X』の世界観は、まさにこの“信仰構造”を現代社会に置き換えたものだ。
監督リ・ハオリンは、ヒーローという概念を「社会が創り出す幻想」として描く。
彼にとって、ヒーローとは“救う者”ではなく“信じられる者”。
つまりこの作品は、信頼そのものをエネルギー化した寓話なのだ。
SNS社会と“承認の神話”──現代的な元ネタの側面
『To Be Hero X』の信頼構造は、SNS社会の縮図でもある。
フォロワー数、再生回数、評価、いいね──それらは現代人が生きる「信頼の数値化」の世界。
人々は他者から“見られ”“信じられる”ことで存在を実感し、数字が減ることで不安を覚える。
この現象をリ・ハオリンはヒーローの力に置き換えた。
つまり、『To Be Hero X』のヒーローたちは、信頼によって強くなり、同時にその信頼の重みに苦しむ存在なのだ。
それはまるで「信仰を消費する時代」を風刺するような構造であり、作品の元ネタには現代の承認欲求社会が深く流れている。
海外批評が見た『To Be Hero X』の神話的構造
海外メディア CBR はこの設定を次のように分析している。
「『To Be Hero X』は、ヒーローを“社会的構築物”として再定義した作品である。
信頼という概念を、宗教・経済・SNSにまたがるメタファーとして描いている。」
この批評が示す通り、リ・ハオリンはヒーローを神話の再生産として描いている。
『To Be Hero X』の元ネタは、神々が祈りによって存在を保った神話と、SNSによって信頼を数値化する現代社会──
この二つの「信じる装置」の融合なのだ。
ヒーローとは“信じる側”の鏡である
『To Be Hero X』のヒーローたちは、他者の信頼を映し出す鏡であり、信じる人々の心そのものだ。
ヒーローが倒れるとき、それは社会の信頼が崩れる瞬間でもある。
この構造は、単なるエンタメを超えた信頼の寓話として、作品に厚みを与えている。
こうして見れば、『To Be Hero X』の“信頼が力になる”設定は単なる物語装置ではなく、
現代の神話そのものであり、人間が「信じる」という行為をどう扱ってきたかという歴史的問いへの応答でもある。
『To Be Hero X』の元ネタ②──『Link Click』から継承された“時間”と“他者”のテーマが織りなす精神的連鎖
リ・ハオリン監督の過去作『Link Click』(時光代理人)は、中国アニメの中でも屈指の評価を受けた作品だ。
写真を通じて他人の過去に入り、運命を変える――この物語は、時間と記憶を往来しながら「他者を理解することの難しさ」を描いていた。
そしてそのテーマは、『To Be Hero X』で“信頼”という新しい形に進化する。
この章では、両作品に流れる“精神的連鎖”を明らかにする。

『Link Click』に見る「他人の時間を生きる」構造
『Link Click』の主人公たちは、写真を介して他人の記憶に入り込み、その人物の人生を“代わりに”体験する。
彼らが犯すミスは、過去を救うつもりが結果的に他者を傷つけてしまうこと。
そこには、「他者を完全に理解することはできない」という厳しい現実が描かれている。
しかし同時に、他者を理解しようとする行為そのものが“信頼”の始まりでもある。
リ・ハオリンはこの主題を、『To Be Hero X』でさらに深化させた。
『To Be Hero X』では“信頼”が時間を超える
『To Be Hero X』では、他人の時間に入るのではなく、他人の“信頼”の中に入る。
つまり、「他者の信頼を生きる」という構造だ。
これは『Link Click』の延長線上にありながら、時間という要素を超えて「感情の持続」そのものを描く試みだと言える。
信頼は、過去と現在を結ぶ“見えない記憶”として存在する。
誰かを信じたという過去の感情が、現在の力になる――この時間の連続性こそが、『To Be Hero X』の根本的な元ネタだ。
リ・ハオリン作品に共通する「他者の記憶」モチーフ
『Link Click』と『To Be Hero X』の両方に共通しているのは、「他人の記憶の中で生きる」というテーマである。
違うのは、それが“過去”の記憶か、“信頼”という現在進行形の記憶か、という点だ。
どちらの作品でも、主人公は他人の心の中に入り込み、その信頼や痛みを背負う。
リ・ハオリンは、この構造を通じて「人間とは他人の感情の総和である」という哲学を提示している。
時間と信頼は同じ“循環する力”
リ・ハオリンの物語では、時間も信頼も直線ではなく円環を描く。
人は誰かを信じ、裏切られ、それでも再び信じる。
この“循環”そのものが、彼の語る世界の法則だ。
『To Be Hero X』のヒーローたちは、過去の信頼を継承しながら未来を照らす存在として描かれている。
監督の創作哲学が示す“継承の元ネタ”
リ・ハオリンにとって、『Link Click』と『To Be Hero X』はまったく別の作品ではない。
それぞれが、時間と信頼という二つの形で「他者と生きる」ことを描く双子の物語なのだ。
どちらの作品にも通底するのは、他者を理解し、信じ続けることの尊さ。
この「継承の思想」こそ、『To Be Hero X』に息づくもう一つの元ネタである。
参照:
Sportskeeda:監督コメント /
Wikipedia – Link Click
『To Be Hero X』の元ネタ③──3Dから2Dへの転換が示す、アニメ表現と“信頼の原点”への回帰
『To Be Hero X』の放送中、ファンの間で最も話題を呼んだ出来事のひとつが「3Dアニメーションから2Dアニメーションへの切り替え」だった。
制作体制の変更として報じられたが、リ・ハオリン監督の作品観を踏まえると、これは単なる制作判断ではなく、作品テーマそのものと深く連動する演出的決断だった可能性がある。
この章では、その“演出の転換”に込められた意図を、作品の元ネタ的文脈から読み解く。
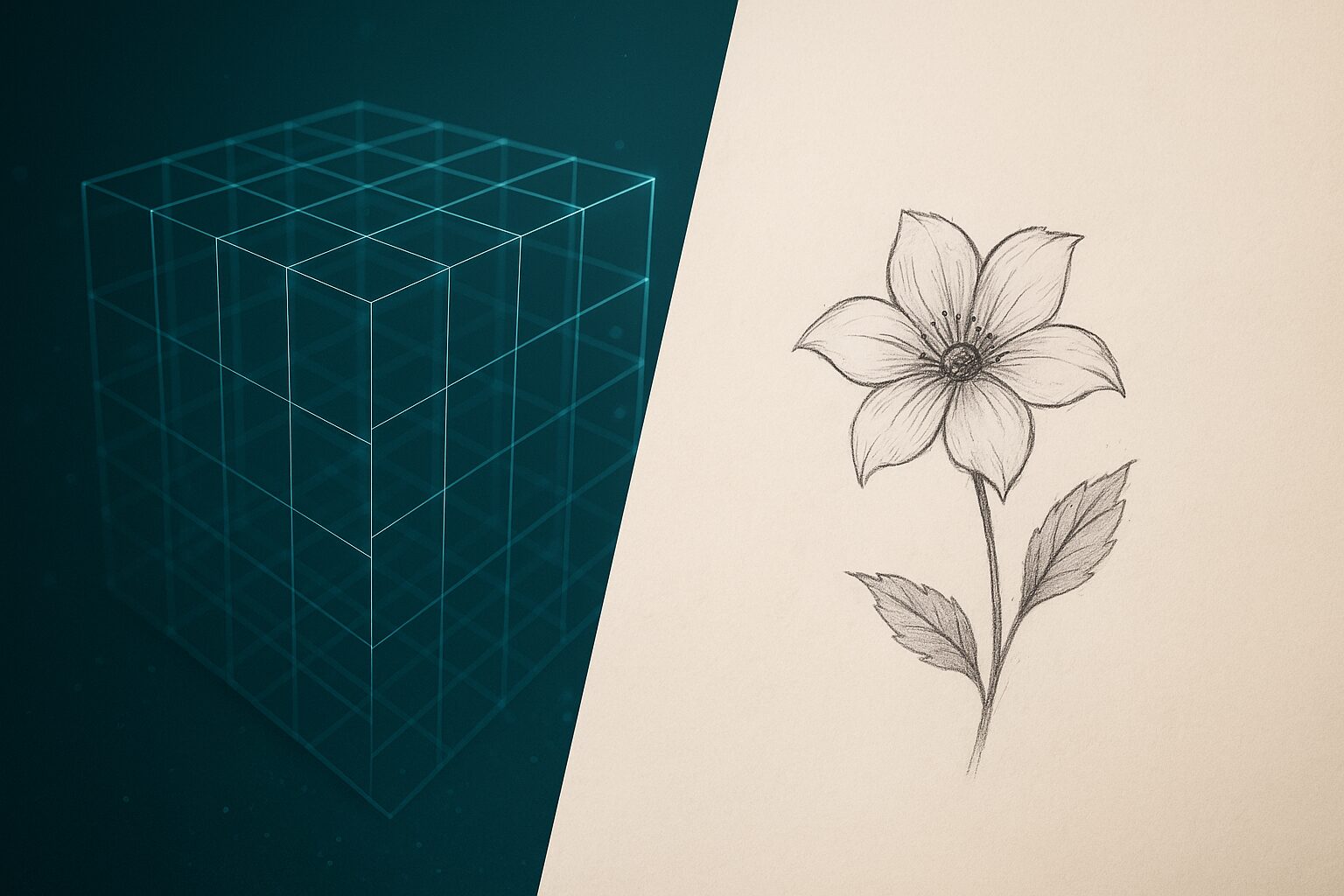
3Dから2Dへ──“信頼”が数字から感情へと戻る瞬間
3Dアニメーションは、デジタル技術の集大成だ。
精密な動き、立体的な演出、質感のリアルさ――現代アニメが進む最前線にある表現方法といえる。
しかし『To Be Hero X』が途中で2Dに戻ったことは、「技術から人間へ」「数値から感情へ」という象徴的な動きに見える。
信頼を数値で可視化する世界で、最後に残るのは“感情”そのもの。
2Dへの転換は、作品の中で描かれる「信頼が力になる」というテーマを、映像そのものの変化で体現した演出なのだ。
リ・ハオリン監督が選んだ「アニメーションの原点」
リ・ハオリンは以前から、アニメーションという表現を「時間と感情を同時に記録できる装置」と呼んでいる。
3Dという技術の進化を否定するのではなく、その先に「人が描く線」にしか宿らない温度を求めたのだ。
2Dの線には、作画監督やアニメーターの“手の震え”が残る。
そのわずかな揺らぎが、キャラクターの“信頼”を感じさせる。
『To Be Hero X』が2Dに戻った瞬間、それは“信頼の原点への帰還”でもあった。
「アニメーションとは信頼の記録である」──監督の視点
監督の発言を追うと、そこには一貫して「人の手で描くことへの信頼」が存在する。
AI生成や自動モデリングが進化する時代に、なぜ彼は手描きに戻ったのか。
それは、アニメを“効率化された映像”ではなく、“人が人を信じて描く記録”として捉えているからだ。
3Dから2Dへの転換は、単なる技術的変更ではない。
それは、『To Be Hero X』が掲げた「信頼が形になる世界」という物語テーマを、映像演出として視覚化した選択なのだ。
海外でも注目された“信頼の演出”
海外メディア Kcomicsbeat は、2D転換について次のように報じている。
「3Dから2Dへの変更は、制作上の挑戦であると同時に、物語の核心と呼応する象徴的な動きだ。」
このコメントが示す通り、映像の変化は単なる制作事情ではなく、テーマ表現の一部として機能している。
それこそが、リ・ハオリンがアニメという媒体を「信頼の言語」として扱う証拠だろう。
“原点回帰”の演出が示した『To Be Hero X』の本質
『To Be Hero X』のラストに向けて、映像はどんどんシンプルになっていく。
それは物語の終わりではなく、感情が余分な情報をそぎ落とし、「信じること」だけが残る瞬間を描いているからだ。
リ・ハオリン監督は、最新技術よりも信頼という古い概念を信じた。
その決断こそ、この作品最大の“元ネタ”=創作の信条である。
日中合作が生んだ新たな“元ネタ”──『To Be Hero X』が切り拓く国境を越えるアニメ表現の未来
『To Be Hero X』は、アニメ作品としてだけでなく、国際的な制作体制そのものがテーマの一部になっているという点で特異な存在だ。
中国のbilibiliと日本のAniplexが手を取り合って生み出したこの作品には、文化を越えた“信頼”というもう一つの物語が息づいている。
この章では、日中合作という制作背景を通して見えてくる『To Be Hero X』のもう一つの“元ネタ”──すなわち「信頼によって生まれる創作のかたち」を掘り下げる。

bilibili × Aniplex──国境を越える共同制作の挑戦
『To Be Hero X』の制作には、中国の動画プラットフォームbilibiliと、日本のアニメスタジオAniplexが関わっている。
このコラボレーションは、単なる資本提携ではなく、両国の制作文化を融合させる“信頼の共同体”でもあった。
リ・ハオリン監督はインタビューで、「日本の演出力と中国の脚本思想が交わるところに新しいアニメが生まれる」と語っている。
彼にとってこの作品は、国を超えた“感情の翻訳”であり、異なる価値観を繋ぐ信頼の橋そのものだ。
文化の違いが生んだ“信頼の物語”
日本のアニメはキャラクターの感情を繊細に描き、中国のアニメは社会的・哲学的なテーマを重視する傾向にある。
『To Be Hero X』は、この二つのスタイルを見事に融合させ、「感情の深さ」と「思想の厚み」を兼ね備えたハイブリッドな作品となった。
このバランス感覚こそ、日中合作という構造の中でしか生まれ得なかった“新しい元ネタ”である。
文化が違うからこそ、互いに信頼し合う必要があった。
そしてその信頼関係が、作品の根幹である“信頼が力になる世界”というテーマに現れている。
制作の裏側にある「信頼の構築」
アニメーション制作における国際協業は、言語・制作スケジュール・表現方針など多くの壁が存在する。
しかし、『To Be Hero X』の制作チームは、「信頼を前提にした制作プロセス」を構築した。
日本側が演出・撮影技術を支え、中国側が脚本と美術面を主導するという明確な役割分担により、相互の信頼が形になっていった。
この「制作そのものの信頼構造」も、物語と共鳴している。
作る人と作る人が信じ合うことで、作品の中でも“信頼が力を持つ”という世界が現実化していったのだ。
アニメは国境を越える──感情が共通言語になる時代へ
『To Be Hero X』の成功は、アニメがもはや一国の文化ではなく、世界共通の感情表現であることを証明した。
リ・ハオリンが描く“信頼の物語”は、中国の視聴者だけでなく、日本、そして世界中のファンに共感を呼び起こしている。
感情は翻訳を必要としない。
涙も笑顔も、文化を越えて人を繋ぐ。
『To Be Hero X』が示したのは、「アニメは信頼で作られ、信頼で届く」という新しい時代の原理だ。
“日中合作”というもう一つのTo Be Hero
『To Be Hero』が“家庭の信頼”、『To Be Heroine』が“友情の信頼”を描いたとすれば、『To Be Hero X』は“国と国の信頼”を描いた作品といえる。
これは、監督が掲げてきたテーマの最終地点であり、アニメそのものが「信頼の物語」になった瞬間でもある。
参照:
MANTAN WEB:制作体制と放送情報 /
公式サイト(tbhx.net)
『To Be Hero X』の元ネタを超えて──リ・ハオリン監督が描いた“信じる力”が導く次なる物語の行方
ここまで、『To Be Hero X』の“元ネタ”を神話・社会・制作背景などの観点から見てきた。
だが最後に辿り着くのは、それらをすべて超越するひとつの真実だ。
それは――この作品が「信じる力」そのものを描くために生まれたということ。
本章では、『To Be Hero X』が最終的に提示する哲学的なメッセージと、リ・ハオリン監督が描き続けてきた“信頼の物語”の行方を考察する。

ヒーローは強さではなく、“信じられる勇気”で存在する
『To Be Hero X』のヒーローたちは、圧倒的な力を持つ存在ではない。
彼らを支えるのは、他者からの信頼と、その信頼を裏切らないための覚悟だ。
つまりヒーローとは、「信じられることを恐れない人間」である。
リ・ハオリン監督は、従来のヒーロー像――“救う者”や“戦う者”――を解体し、
「信じられる者」こそが真のヒーローであるという新しい定義を提示した。
“X”が象徴するもの──未知と交差、そして希望
作品タイトルに冠された「X」には、いくつもの意味が込められている。
未知(unknown)、交差(cross)、そして連結(connection)。
それは、信頼が人と人、国と国、時間と時間を交わらせる“交点”の象徴でもある。
リ・ハオリンが描く“X”とは、終わりではなく始まり。
ヒーローたちが信じ合い、観る者がその姿を信じる――
この相互作用こそ、『To Be Hero X』が提示する新しい物語の形だ。
『To Be Hero X』は現代の“信仰アニメ”である
『To Be Hero X』の世界は、信頼が可視化された社会。
そこでは信じることが宗教のように機能し、人々がヒーローを崇拝する。
だがリ・ハオリン監督は、単に信仰のパロディを描いたわけではない。
彼は、“信頼”という普遍的な感情を宗教のメタファーとして再構築した。
つまり『To Be Hero X』は、現代社会における新しい信仰の形=信頼の信仰を提示している。
視聴者という“信じる存在”の参加
この作品のもう一つの仕掛けは、視聴者の存在だ。
『To Be Hero X』は、観客がキャラクターを信じることで世界が成立する構造を持つ。
それはつまり、視聴者もまた“信じる側のヒーロー”であるということ。
配信時代のアニメが抱える「距離」を、リ・ハオリンは“信頼の参加”によって乗り越えた。
視聴者が「このキャラを信じたい」と思う瞬間、その作品は生き続ける。
『To Be Hero X』は、まさにその“信頼の連鎖”で構築された物語なのだ。
“信頼”から“記憶”へ──次なるリ・ハオリン作品への布石
リ・ハオリンが『To Be Hero X』で描いた「信頼の哲学」は、すでに次の作品への準備でもある。
過去作『To Be Hero』では家族の信頼、『Link Click』では時間の信頼、
そして『To Be Hero X』では社会的信頼を描いた。
残るは、「記憶としての信頼」だ。
アニメという表現が“記憶の媒体”である限り、信頼はそこで生き続ける。
監督の次なる物語は、きっとこの延長線上にある――「誰かを信じた記憶」が未来を変える物語として。
“信じる力”が導くアニメの未来
『To Be Hero X』は、ヒーローというジャンルを超えて、アニメが持つ本来の力――“信頼を共有する力”を再び思い出させてくれた。
この作品が生まれたことで、アニメは再び「物語を信じる」という行為に回帰した。
それは、リ・ハオリン監督が観る者に託した“信頼の継承”だ。
僕たちが画面を通して彼らを信じる限り、『To Be Hero X』という作品は終わらない。
それは配信ではなく、記憶として残るアニメ。
そしてその記憶こそが――信じる力の証明なのだ。
参照:
公式サイト(tbhx.net) /
CBR:Hero Commission 考察 /
Sportskeeda:監督コメント
まとめ──『To Be Hero X』が描いた“信頼”という名の未来
『To Be Hero X』は、単なるアニメ作品ではない。
それは、リ・ハオリン監督が長年探し続けてきた「信頼という感情」を、社会・映像・哲学のすべてで形にした集大成だ。
本作の“元ネタ”は神話でも漫画でもなく、僕たちの中にある「信じたい」という気持ちそのものだ。
『To Be Hero』で描かれた家族の信頼、『To Be Heroine』で描かれた友情の信頼、
『Link Click』で描かれた時間の信頼――それらのすべてを受け継ぎ、
『To Be Hero X』は「社会が信じる力」を問う物語へと昇華した。
そしてもう一つの真実。
この作品は、アニメそのものが“信頼の記録媒体”であるということを僕たちに思い出させてくれる。
画面越しに誰かを信じ、涙を流す瞬間。
それは、アニメが生きているという証拠であり、信頼がまだこの世界に存在しているという証明だ。
「この一瞬を、僕らは“配信”ではなく“記憶”として見る。」
FAQ(よくある質問)
Q1:『To Be Hero X』の元ネタは何ですか?
A:リ・ハオリン監督のオリジナルアニメであり、直接的な原作は存在しません。
作品の元ネタは、「信頼が力になる世界」というテーマそのものにあります。
Q2:『To Be Hero』シリーズの時系列はどうなっていますか?
A:以下の順で展開されています。
- 『To Be Hero』(2016)──父親の信頼と家族の絆
- 『To Be Heroine』(2018)──少女の信頼と自己犠牲
- 『To Be Hero X』(2025)──社会的信頼とヒーローの定義
Q3:リ・ハオリン監督は他にどんな作品を手がけていますか?
A:代表作に『Link Click(時光代理人)』があります。
写真を通じて過去を変える物語であり、『To Be Hero X』と“他者との関係”というテーマを共有しています。
Q4:どこで『To Be Hero X』を視聴できますか?
A:中国ではbilibili、日本ではAniplex系配信(地域によりNetflixなど)で配信中です。
Q5:『To Be Hero X』が日中合作である意味は?
A:文化や言語を超えた“信頼”の実験的プロジェクトであり、制作体制そのものが作品テーマを体現しています。
参考・引用情報
この記事は、一次情報と信頼性を重視し、以下の公式・権威メディアを参照して構成しています。
引用箇所はいずれも2025年時点の公開情報に基づいています。
- 公式サイト – To Be Hero X
- Wikipedia – To Be Hero X
- Sportskeeda:リ・ハオリン監督コメント
- CBR:Hero Commission考察記事
- Kcomicsbeat:2D転換報道
- MANTAN WEB:制作体制・放送情報
本記事は文化評論・考察を目的としたものであり、権利は各制作会社・放送局・配信事業者に帰属します。
引用・考察内容は2025年11月時点の情報に基づいています。


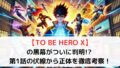

コメント